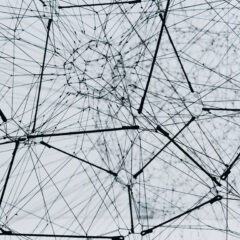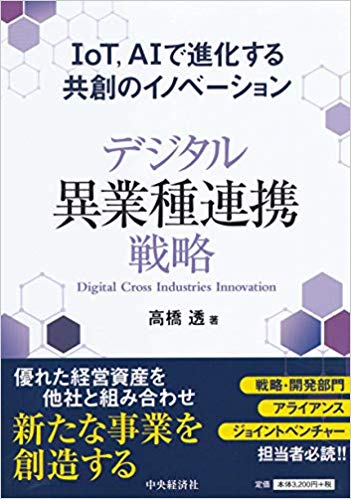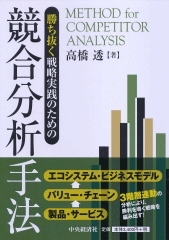高利益を達成するための生産財マーケティングとは(1) 顧客の事業課題、ニーズを探って“束”にしよう
ニューチャーネットワークス 取締役 シニアコンサルタント
福島 彰一郎
昨今の為替の変化というのは実に荒っぽいもので、あっという間に1ドル110円になり、今度は「円安すぎる」という声が中小企業から出てきている。
円高の時代が長かったせいか、日本企業の多くはその環境に対応するために輸出型から海外拠点でのドルベースのビジネスにだいぶ構造転換しており、円安になってきた現在、多くの企業にとってメリットは少ない。中小企業の中にはかなり危機的な状況に陥っているところもあり、輸入材の値段が上がってビジネス的に好ましくないのが実情だ。
為替の調整は官に任せるしかないが、生産財メーカーとしてはこのように激しい事業環境であっても、十分な利益を出せるだけの付加価値のある製品を継続的につくっていかなければならない。それが基本戦略である。しかし、弊社がコンサルティングを通じて国内生産財メーカーの担当者に会って話を聞くと、この基本戦略を十分に実現できていない企業が多い印象を受ける。
今回からの連載コラムでは、高利益を上げるために生産財メーカーが押さえるべきマーケティングのポイントについて、特に製品企画に携わっている技術者をイメージして紹介していきたい。
メルマガ会員登録
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。