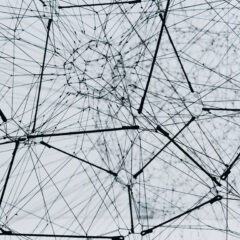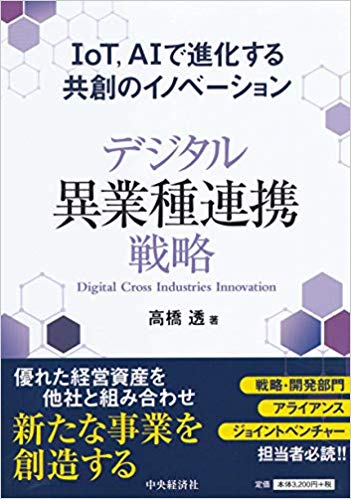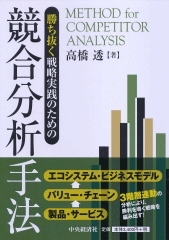勝ち残る企業に求められるサステナビリティの視点 ~CSRの先にある企業経営の本質~
~はじめに~
私が代表をつとめる株式会社イースクエアでは、2001年より様々な業種業態のクライアントのCSR(企業の社会的責任)経営の推進を支援している。我々の考えるCSR経営とは、自社のサステナビリティ(持続可能性、*1)を高めるとともに社会のサステナビリティにも貢献する企業経営のことを指している。この10年間で、企業を取り巻く事業環境は大きく変化してきた。深刻化する環境、社会問題を背景として、実質的な制約条件が厳しくなり、企業を取り巻くステークホルダーの影響力が増すなかで、従来とは違うアプローチが企業経営に求められている。CSR経営で一歩リードする欧米の企業が、どのような観点で企業経営を行なっているのか、事例を交えながら本稿を進める。
■なぜ今「CSR」「サステナビリティ」なのか
CSRやサステナビリティについての議論がここ数年の間にぐっと進展し、企業経営や事業戦略の根幹にしっかりと組み込まれる時代になってきたことを強く感じている。企業は様々な観点からサステナビリティに向き合わなければいけない状況となっている。
その背景としてまず第一に挙げられるのが、今まで当然のものとして存在していた我々を取り巻く地球環境、すなわち自然資本が毀損し、企業活動の基盤が崩れつつあるという現実である。現在、年間およそ3兆ドルの自然資本を毀損させていると言われている(2010年COP10会議より)。これは世界のGDPの約5%に当たる額で、いかに巨額であるかをご理解いただけるだろう。我々は自然資本から生み出される動植物、遺伝子などの原料、浄化された空気・水などを使って経済活動を営んでいるわけだが、その基盤がどんどん腐食されてしまっているのだ。
第二に挙げられるのは、こういった自然資本としての生物多様性を失うことが、貧困などの社会問題を助長することにつながり、結果として企業への間接的なコストアップにつながっているということである。生物多様性というと少し分かりづらいが、つまり地球の色々な所で色々な生き物が存在していることを意味している。生物多様性が劣化すると、生態系から得られるサービスが少なくなってしまう。例えば、製薬会社であれば、遺伝子資源を自然の中に取りに行き、それを使って薬品を開発している。食品会社は生態系の中で育まれる動植物を原料として使用している。それ以外にも木材や水など様々なものを我々は使っていることを考えても、生物多様性の劣化は直接的・間接的にすべての産業に影響があることが分かる。
また、世界中の貧困層の約70%は、農業や畜産、森林関連分野など直接自然資本に依存する生活をしている。自然資本が毀損されることで、彼らの生活基盤を深刻に脅かすことになる。貧困が増えれば当然、経済への負の影響やセキュリティの問題が増大する。すると企業はより多くの間接コストを払わなければならない。自然資本の毀損や生活の不安定化は、全て企業の経済活動に影響を及ぼすこととなる。
第三に、こういった問題に対する企業への期待が今まで以上に高まっているという背景が挙げられる。かつては環境、社会問題への対応は政府に頼っていればよかった。しかし、「政府の政策に頼っていて本当に大丈夫なのか」という疑問を誰しもお持ちであろう。世界的に、良い意味でも悪い意味でも企業に期待するところが非常に大きくなってきている。その期待に応えられるか否かによって、企業のレピュテーションを高めるチャンスとなる一方で、期待にうまく応えられないとリスク要因となってしまう。
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。