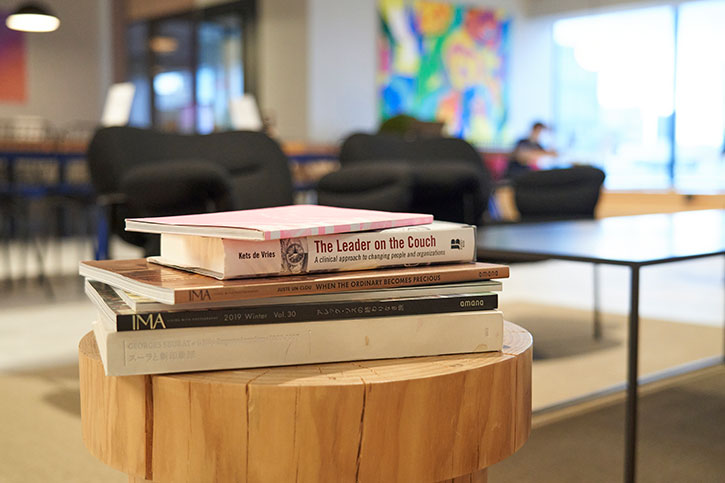
グローバル・マーケティングにおける「共通化戦略」と「カスタマイズ戦略」
新商品・新事業開発「グローバル・マーケティング」
2012年は国内市場の「六重苦」を背景に、製造業の海外M&Aが活発であった。今後も、自民党の新政権が主導する金融緩和によって、企業の資金調達はますます容易になる。グローバルでの成長を志向する企業が、潤沢な資金を海外M&Aに活用しようとする流れはまだまだ続くだろう。
しかし、海外に活路を求めるために行動を起こしても、それが事業としての実を結ぶかどうかは定かではない。戦略をともなった行動でなければならない。特に国内とは勝手の異なる海外市場向けのマーケティング戦略が重要であることは異論を挟まないであろう。
そこで今回から数回にわたり、グローバル・マーケティングの考え方を紹介していきたい。
1.グローバル・マーケティングとは
グローバル・マーケティングとは、国内市場も世界市場の1つととらえて、国境を越えたマーケティング戦略を構想し、意思決定し、行動する組織活動である。そこでは国内市場と海外市場という区別ではなく、日本国内も一つの市場であり、「日本市場」という言い方になる。
国を超えて海外でマーケティングを行うときの特徴は何であろうか。それは、そこに「差異」が生まれるということである。差異とは、①文化的差異、②制度・政治的差異、③地理的差異、④経済的差異の4つである。
文化的差異の要素は、生活習慣や嗜好などである。食品やファッションなどは文化的要素の影響を受けやすい。一方、素材や電子部品などの生産財は顧客が企業であるために文化的要素の影響は小さい
制度・政治的要素は、国の法制度や政治、政策などの要素である。社会インフラや軍事、天然資源のように国家レベルでの戦略的な役割が大きい産業は、制度・政治的影響を受けやすくなる。
地理的差異は、気候や輸送距離・コストなどの要素である。鉄や銅などの製品の体積に対して付加価値の小さい製品は輸送コストが影響する。
経済的要素は、その国の労働賃金や生活者の可処分所得などの要素である。生産工程が労働集約的な組立加工などの場合、労働賃金の低い国で工場が建設される。また可処分所得が大きければ、付加価値の高い耐久消費財が売れるようになり、先進国企業にとって事業機会となる。
グローバル展開ではこのような「差異」が必ずあり、差異へ対応、あるいは差異の積極的利用を図った戦略を工夫することになる。
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。











