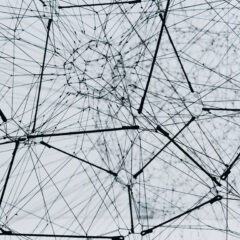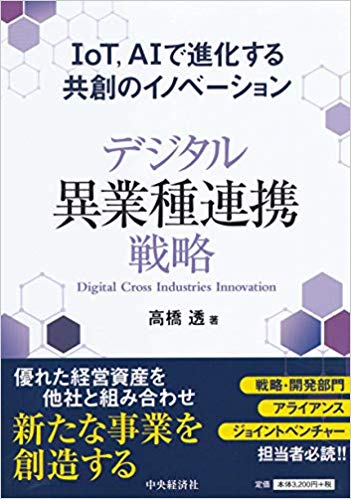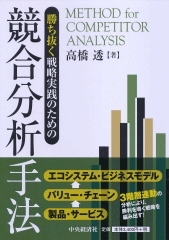「製造業における知的財産戦略の基本的考え方」(1)
2009年1月29日に弊社にて開催いたしました「グローバル・エイジセミナー」におきまして、「企業活動における知的財産の本質とは何か」について、日本の知的財産分野におけるカリスマでいらっしゃるキヤノン株式会社顧問の丸島儀一先生にご講演をいただきました。
私もこれまでに数回丸島先生のお話を拝聴しておりますが、先生のお話は豊富な実務経験に基づいた、具体的で且つ非常に本質を突かれたお話であり、事業・知財・研究開発などの関わりの考え方などについて深く感銘を受けた記憶があります。
今回から計3回にわたり、講義内容を是非皆様にご紹介させていただきたいと思います。
ニューチャーネットワークス 福島 彰一郎
■ 1960年台における知的財産
私が知財の世界に入ったのは、1960年でした。当時は、事業と知財を併せて考えていた人はいなかったと思います。少なくとも口に出してそういう ことを言っていた人はいなかった。知財という言葉もなかった。特許という言葉はあったけれども、私自身が会社に入ったときには特許のことも全然知らなかっ た。技術系だったので技術開発がやりたいと思って入ったのだが、特許をやっていた先輩がみんないなくなり、私に配属命令が同期入社の人より早く来たのでし た。分からないところからの始まりだったので、何をいったいやるのだろうか、という思いでした。ノーベル賞級の発明に対して権利を与えるようなものかと漠 然と思っていた。特許庁があるのも知らなかった。私は公務員試験も受かっていたので、特許庁を知っていたら、たぶん入っていたと思う。でも、担任の先生が 防衛庁へ行けと言うことで、防衛庁の研究所かと思っていたら、調達局だといわれた。「そこで何をするのですか?」と聞くと、「あそこは羽振りがいいぞ」と 言われた。自分としては関心ありません」と返事した。もし入っていたら、今頃話題になっていたかもしれません、これは冗談です。
ちょうど会社に入ったときに、たまたま特許室にいた先輩たちが活発に活動したせいか、どこかから特許室がおかしいぞという非難が出ました。そこで 外部の専門家に監査をしてもらいました。その結果、あまりにも乱雑な仕事をしているため、「特許課は仕事するな」と社長から命令が出ていた時でした。「仕 事するな」という意味は、出願明細書を書くなどの対特許庁への手続きをするなということ。そのため、やることが殆どなくなってしまっていたのです。そこ で、私が机に座って最初にしたのは特許公報を見るということでした。
今はもう紙の公報はなくなりましたが、私の特許に対するイメージが ガラっと変わったのが、公報でした。週刊誌なみの厚さがあり、しかもそれがカメ ラの関係分野だけでその厚さだったこと、さらに中身を見て、「なんだ、この程度か」という内容だったこともあります。これであれば自分でも発明できるなと いうふうに思ったものでした。
当時の特許課の仕事というと、開発部門にその公報を配達してみてもらう仕事、発明者が発明した提案書類 を特許事務所の先生に届ける仕事、その先生 が書いた原稿を発明者に届けてチェックしてもらう仕事だった。仕事がおもしろくないので、課長に部署異動を頼んだが、当時特許部門に希望して入ってくる人 はいなかったので、入ってきたら変えてあげるのでそれまで我慢しろと言われ、我慢して仕事していました。特許公報とかを見てどんな技術があり、それがどう やって権利化されているかということを勉強しました。さらに出願明細書の原稿作成をお願いしていた2人の弁理士の先生が書いた原稿をみて勉強しました。す ると弁理士の先生が違えば原稿の書き方も随分、異なることが分かりました。1人の先生は、極端な造語ばかり使っていた。読めば理解できるが辞書には載って いない言葉だった。それをみて、特許とは造語の世界なのかなと思ったこともあった。もう一人の先生は易しい言葉で明細書を書いていた。一人の先生からは、 特許明細を書けるようになるには、「ものがどうやって結合され、どう動くかが上手く表現できないとダメだよ」と言われた。ノートにメモを取り、そのための 表現を一生懸命勉強した。ある時、もう一人の先生の原稿を見ると、抜けている部分があることに気が付きました。そこに追記してほしい、と記載されていたこ ともあった。そこで技術を理解していなくても明細書を書く人もいることに気がついた。まあ、いずれにしてもたいした仕事ではなかった。一番悩んだのは、カ メラ業界ではドイツの特許公報が一番重要だったため、ドイツ語の公報が結構入ってきていたことでした。
当時、設計をやっていた人が3月 に異動してきて課長となり、特許課ができ、自分が6月に配属になった。二人とも素人であった。先輩の女性は、英語 ができる方であったこともあり、外国出願の翻訳をやっていた。もう一人は先行技術を調査する担当の方であり、図書室と兼任だった。合計4人体制だった。
実質的な特許の仕事をやるのは課長と私の2人であったが、素人でもあり何をしていくのか、よく分かりませんでした。まずは開発部隊へのサービスを 行なって勉強していきました。公報を見る限り、このレベルなら自分にもできると常々感じており、「社長に内緒でちょっと仕事しませんか」と課長に話をしま した。特許の出願は社長に禁止されているので、では、異議の申し立てをしようということになりました。異議の申し立ては公告になった他社の特許に対するも のなので禁止命令の範囲外だと思ってやってみました。これの成功率が非常に高く、8割以上。なぜそんなに成功したかというと、ちょうど、われわれの資料室 に縦書きの明細書の特許公報が沢山ありました。それをみると、ドイツのカメラ会社のアイデアは結構将来のことが書いてあった。しかし実現する方法が「メ カ」しかなく、何とか無理矢理「メカ」でやっていた。「こんなにいっぱいアイデアはあるんだな」ということに気が付いたのです。証拠として使ったのはそう いう先行技術で、公告されたものに対して、そういう先行技術を利用してどんどん潰していくことができました。人の財産を潰すのは別に自社の財産に係る訳で はないのだから良いだろうということで、その仕事は継続し、結構成功したのでした。そして、そろそろ出願しても良いのではないか、ということで内緒で、出 願書類を書き始めたのでした。
■ 新規事業としての複写機事業の取り組み
そんな頃、新規事業の話が出てきました。1番目の新規事業は失敗であったが、社内の定義では、当時採用した技術者が他の分野で非常に活躍したこと や、工場を建てるために買った土地をその次の事業で利用できたので、失敗とは言わずに短命で終わったという表現をしていました。時期が早かったのか、マー ケットリサーチが不十分であったためか、新卒の給料が1万円程度の時に、20~30万円した商品だったということもあり、売れなかったので止めたのでし た。
第2の新規事業として経営者が一生懸命考えて、消耗品付きの事業がやりたいということになりました。カメラ事業をやっている時にコダック社にカメ ラはフィルムバーナーだと感謝されていたこともあり、そこからの発想だったと聞いています。そこで2番目に取りかかったのが複写機でした。これはRCAが 開発してライセンスしてくれたので、日本の事務機メーカーのほとんどがライセンスを受けて製造していました。現像方法には、乾式と湿式がありました。乾式 はRCAのライセンスでできたのだが、湿式はリコーさんがオーストラリア政府の研究所から日本での独占ライセンスを受けて日本市場を独占しており、サブラ イセンスを他社になかなか出してくれなかった。湿式は乾式と比べ臭いが嫌だという人もいましたが、当時乾式は現像材の粒子をあまり細かくできず画像が綺麗 ではありませんでした。一方、湿式は微粒子なので画像をきれいに現像できるというメリットがありました。
■ ゼロックスの普通紙の乾式複写機
そこにゼロックスが乾式の複写機を出してきました。RCAタイプは乾式といってもコピー紙が感光紙なので非常に紙が重かった。そこに普通紙の乾式 の複写機が出てきた。これはどう見ても事業として勝てるわけないと判断し、経営者から乾式のコピー機(普通紙)開発命令が出ました。私がもう少し特許を勉 強していれば、「特許マップを見たら真っ黒で隙がないから辞めなさい」といったかもしれないが、そんなことを検討する前に経営者から命令が出ていたので、 「はい」と言わざるを得なかった。検討してみると、やはり特許マップは真っ黒だった。しかし、開発命令は出てしまったので、その特許の壁を越えないといけ ないということになり、プロジェクトが立ち上がり、そのプロジェクトに参加して私が研究開発者と連携しながら、どうやって特許を突破したらいいかという検 討からプロジェクトを進めていきました。開発陣も含めて特許の読み込みを丹念に行い、先行技術と先行権利を認識いたしました。それが後に大きな効果となっ たのでした。
当時カメラの特許状況はどうだったのかというと、真面目な業界でした。みんな特許を大事にしていましたが、当時の技術が成 熟期にあったため特許の 意味は「デッドコピー(開発の手続きをとらずに造られた単純な模倣品・複製品)」防止程度でした。要するに自分の開発成果をそっくりまねされないようにと いう位置づけでの特許だった。その程度であったこともあり、人の特許があっても、その特許を気にしないでいくらでも事業ができた。カメラのレンズについて は、開発余地があったため、カメラ業界ではレンズの特許が大事にされた。これは絶対ライセンスしないというのが業界の流れでした。でも、別に人の特許を使 わなくても事業はできるというのがカメラ業界だったのです。
一方、複写機の場合は、ゼロックスが特許で乾式の技術を独占していまし た。しかも、ライセンスをしなかった。カメラ業界ではデッドコピーを防ぐ位 の影響力しかない特許が、複写機業界では事業全部(乾式の普通紙複写機)を独占しており、非常に対称的なのでした。その分野に事業参入しろという経営者方 針であったのですが、特許に触れたらライセンスをもらえないし、事業が出来ない。それで、ゼロックスや他の企業の特許を一生懸命検討した。幸い、当時は電 子写真技術を取り扱う企業もそんなに多くなく、特許の件数も今のように多くなかったので、一応検討できる対象ではありました。
■ ゼロックスの特許の超越の挑戦
まず、ゼロックス特許をどやったら超越できるかを考えてみました。まずゼロックスの使っている「カールソンプロセス」から検討したのでした。ゼ ロックス自身、「カールソンプロセス」を開発したのではなくて、カールソンという人から買い取ったのです。RCAのプロセスと何が違うかというと、感光体 に電気的潜像をつくって、現像するところまで同じです。その後、可視化された像を普通紙に転写する工程がゼロックスのやり方なのでした。そして転写された ものに粒子を定着させる。ドラムを再利用するために感光体のクリーニングという手段が加わっている。クリーニングしたあとの感光体は、再度潜像形成に利用 され、またコピーをとる。RCAのプロセスには、転写のプロセスとクリーニングというプロセスがなかった。そこがゼロックスの基本特許となったのでした。
そこでキヤノンとしては、繰り返し使用に耐える感光体を早急に作らなければならなかった。私どもは将来のカメラの受光素子のために、ゼ ロックスの 使っているセレンよりも感度の高いCdSという材料をもっていた。しかし、CdSは柔らかくて、繰り返し使用に耐えられなかった。そこでCdS表面に絶縁 層を巻いてみた。しかし、カールソンプロセスで像を出そうとしたら、像が出ない。「これではまずい」と思ったのと同時に「しめた!」と思った。もしこの感 光体で像が出たらゼロックスとは全く違うといえるということで、いろいろ像出しのプロセスを考えた。5通りぐらいでてきた。その1つだけでなく、後の4通 りの方法も特許を出願することができたのでした。
その後、開発は進み、最後に苦労したのはクリーニングでした。繰り返し使用するときに 感光体に残ったトナーをどのようにして落とすかであった。当 時ゼロックスはどのような手段を使っていたかというと、アンゴラウサギの毛を円筒状に巻いて高速で回転させて、柔らかく吹き飛ばしていた。それを回収する フードもついていた。これを真似したら特許に引っかかってしまう。他の手段を考えて、最終的に考えたのはゴム板です。しかし、このゴムブレードだったら全 部出来るのではなくて、ドラムに対してどのような角度でブレードを接触させるかがポイントなのです。ドラムをなでるようにしたのではクリーニングできな い。逆に、刺さる方向にすると、クリーニング効果が凄く出る。これにより、クリーニングが完成して、事業開発を進めることが出来ました。
■ 第三者の特許を飛び越える開発
これを今振り返ってみますと、事業化ができたということはもちろん大事なのですが、むしろ、第3者の特許を飛び越えて、新しいものを造り出したと いう、開発のプロセスがすごく財産として残ったのです。クリーニングの特許を出したとき、特許庁に行って、面接して頂いた。「自動車のワイパーとどう違う のか?」と言われました。来るだろうと分かっていましたが、「自動車のワイパーは自然に撫でているだけ、あのような方向ではクリーニングできません」とい いました。すると「机の上にチューイングガムが着いたら、どうやって取る?なでないだろ、こうやってとるだろ」と言われた。方向性は同じですね(刺さる方 向)。しかし、そこまで分解して先行技術があるよといわれると特許は一つもとれない。反論して特許にはなりました。
なぜこの特許の話 をするかというと、技術的に高度でなくても使用して技術的、経済的効果が大きい発明の特許が大事だと言うことを強調したいからで す。私が最初に思ったノーベル賞級のものは特許になるだろう、会社の中でも技術的に高度なものが特許になるだろと思っている人はいる。ところが、ブレード はゴム板1枚です。これは聞いたら誰でも分かります。技術的に高度だといえません。でも私の認識ではいまだに、転写方式のプリンターや複写機において、こ れに勝るクリーニング装置は出ていない。何十年も経っており、基本権利は切れています。でも、これより勝るクリーニング装置は出ていない。なぜかという と、動力いらない、固定でよい、スペース取らない、安い、それから音も出ない、エネルギーも使わないし、小型にできる。技術的にはだれでも理解できる。事 業につかうとすごい経済効果がある。
■ 流体現象の乾式複写機の開発
更にこのブレードができたことによって、どういう製品に貢献したかというと、その後、世界で初めて液体現像の乾式の複写機を開発したのです。こ れは液体現像しますから、クリーニングは必要です。ゼロックスのクリーニングは「ウサギの毛」を使っているので、びしょ濡れになってしまいクリーニングで きないのです。ゴム板は、ちゃんとクリーニングできる。これを「リクドライ」と名前付けて、湿式現像方式の乾式複写機というのを世界で初めて造ったので す。
本来電子写真方式の複写機は感光体、現像材、コピー紙が相互に静電気、温度、湿度等に大きく影響されますのですり合わせ技術が重要 になります。 初めて造ったこともあり、技術が安定していません。ですから、頻繁にサービスに行かないといけない。まぁ大量のコピーをとってくれるお客様ならサービスマ ンがいってもペイするのですけれど、コピー量の少ない家庭に普及させたいと思っていた。それには小型化しなければならない。小型化で一番ネックになるのは クリーニング装置。そこでゴム板が大きな貢献をしたのです。お客さんが故障を自分で直せるようなサービスフリーの機械を考えて造り出したのが、プロセス カートリッジです。要するに、一番不安定である心臓部を一つのユニットにしてしまった。この小さいユニットで出来たのもブレードのお陰なのです。これによ り家庭用の複写機ができた。そういう貢献もした特許。サービス費用を低減できたことも考慮すると、一番経済効果の高かったのはこのブレードクリーニング。 でも、一番簡単な特許ではなかったかと思います。
もちろん、技術的高度なものは価値がないといっているわけではありません。ですが、トランジスタの発明もそうですけれど、ノーベル賞級の発明だ と、すごい権利はとれますけれど、事業化するときには権利がなくなっているかもしれません。日本の場合は出願して20年したらエクスパイヤーしてしまうか ら、発明してから20年以内に事業化しなかったら何の価値もなくなってしまいます。では技術的に高度な物を大事にするにはどうしたらよいのでしょうか。 ノーベル賞級の発明を事業化しようと思ったら、どういう戦略が必要なのか。これは開発型の最先端の研究成果を事業化するのとは全く違ってきます。このこと については後ほどご説明いたします。
■ ゼロックスの対抗戦略
いずれにしても正規に事業が立ち上がり、概要を発表をしました。確か経団連で発表しました。その時、ゼロックスさんから見に来たいと連絡があった ので、NDA(秘密保持契約)を結んで見に来ることをOKしたのです。土壇場で、その技術者がNDAにサインしないで行ったので、NDAがない範囲でいい から見せてくれという話になってしまった。では経団連に発表した程度のものを見せようと考えたのです。このゼロックスの技術者は交渉がうまい。当時の日本 の技術者はプライドばかり高いというか、言わなくていいことをしゃべってしまう。そんなことも知らないの?と言われたらたまらないです。「知ってる!」と いってしゃべってしまう。知っていても知らないと言ってほしいのですが。このあたりが、私も初めて外国の技術者に接した時です。交渉がうまい。日本の技術 者はまんまとそれに引っかかっているのです。
その結果、内容が全部わかってしまった。そしてゼロックスがどういう対抗戦略をとってきたか というと、自分のペンディングの特許を加工して、キヤ ノンのプロセスとぴったり合わせた内容に補正してきたのです。この補正をドイツ、イギリス、オーストラリアではトライして、失敗しました。アメリカでは特 許が確定してから1年以上経っていましたのでクレーム(特許請求の範囲)を広げられないのです。アメリカの本元の特許は使えなかったのでした。
日本は当時公開制度がなかったから、出願内容が潜っていて分からない。ある時点で公告になって出てきた。そしたらゼロックスとキヤノンの出願内容 がそっくりなのでした。ゼロックス側の審査の過程を調べたら、審査官に拒絶されていました。拒絶査定不服の審判でも拒絶され、東京高裁に審決不服の控訴を 2度までしていた。東京高裁にいくと、特許庁の要旨変更の拒絶審決が覆され、さし戻された。2度目も別の要旨変更を理由に拒絶審決したが又覆され、差し戻 された。もともと書いていないことを増やしたということで、要旨変更という理由で拒絶ができるのです。当時、特許庁の技術的な判断は正しいのですが、裁判 所が問題です。技術的な理由ではなく審決の書き方で判決を出していた。審決にどう書くか、その書き方がまずくて戻されているのです。2度戻ってきて、それ に審判官もくたびれて、通さないといけないかというときだった。しかし、キヤノン側としては通ったら大変なことになる。必死に防衛して、結果的にはまた新 しい審判長が、拒絶査定して一件落着となりました。
一つ助けられたのは、アメリカがプロパテントの時代ではなかったことです。プロパテントの時代でしたら、もっと訴訟をやっていたはずです。
■ ゼロックスとのクロスライセンス
このケースでは、交渉で済み、結果的にはクロスライセンスをして、一件落着したのでした。どうして相手がクロスライセンスを欲したか、どうして特許群で独占していた特許網を突破できたか、これがポイントです。
一つは、技術が進歩しているからです。技術進歩において、特許は一段階ジャンプしたところの技術の特許を取っているだけなのです。その後、技術は どんどん進歩しているのです。ゼロックスが最初に市場投入した複写機をみると、まだ技術進歩が途中の商品なのです。そこでは「いたわり」の技術を使用して いたのです。例えば、感光体のセレンは、繰り返し使用には耐えましたけれど、いかに物理的な衝撃を与えないかのプロセスで成り立っていたのです。ここで一 番の問題は、転写です。転写で圧力をかけるとドラムが痛む。さらなる問題としてはクリーニング。クリーニングにおいて「うさぎの毛」を使用して感光体を傷 つけないようにしていた。ブレードクリーニングでやると感光体が傷ついてしまい、繰り返し使用できない。
逆に、私たちはドラムの表面を 絶縁層で堅くしたのでした。ある意味では感光材料の完成度があがった状態と同じ状態を表面的には作ったのです。そし てその開発成果として周辺の実用化の特許も沢山持っていたから、ゼロックスがセレンの完成度を上げたときにブレードでもクリーニングできるようになったら 私どもがとった知的財産は、結構将来的には役立つということです。
私どもはこれで、特許係争を一段落つけました。互角の立場に立った。ゼロックスさんの特許を無償で使用できたのはうちだけだったと思います。これにより特許上はご破算で、これからが競争だという立場になりました。
■ 事業・研究開発・知財の三位一体の活動の重要性
振り返ってみて、事業が安定して、ゼロックスの特許の参入障壁を避けられたのは良かったのですが、一番の成果としては、研究開発者と知財が一緒に なって、知財の検討から研究開発を始めたと言うことなのです。先行技術が、頭に入りました。権利書というものを飛び越える力が付きました。
例えば「ある設計をしなさい」と技術者の前に特許公報を並べると、どういうタイプの技術者が出るのでしょうか。三つタイプがあるだろうと思いま す。1つはギブアップするタイプ、こんなに沢山特許があったら、私はできないと言う一番素直な技術者です。この人は役に立たない。もう1つは要領のいい人 で、どこか真似して早く成果は出す。しかし、これを事業にしたらすぐ権利侵害で訴えられてしまう。これもだめです。望ましい技術者は権利情報を技術情報に 変換することができる技術者です。
特許の権利書には請求範囲というものがあります。そこに発明の技術思想が文章で表現されているので す。その文章をみながら、技術思想を見抜くのが 難しい。技術思想を見抜いて、現実に、特許がどういう押さえ方をしているかを把握します。技術思想で押さえていない特許は他の手段で突破できる可能性があ ります。
もう一つは、技術が進歩していますから、当時では実現できない周辺の技術が進歩することによって、思想を別な方法で、実現で きるというチャンスが でてきます。例えば、我々の業界でいうと、半導体の進歩と、ソフトウェアです。これで、先ほど言ったカメラの分野でやりたいことが何でも出来るようになり 技術開発が活発になった。周辺のいろんな技術進歩によって、従来はとりえなかった技術が採用できるということです。これにより結構、特許は、突破できると いうことです。
逆の見方をすると、今、発明して権利を取ってもすぐに突破されるのでは、おもしろくない。突破した技術者が今度は自分の 成果を他人に突破されない ぞ、と思うようになりました。知財の担当者がそう思うのも大事だと思うのですが、研究開発者がそう思うことが、一番大事です。これがプロジェクトの一番大 きな成果なのです。そのときに、ゼロックスの事業ということを前提に行っていたので、事業意識もすごく大きかったこともあります。当然、複写機を事業化し ようという前提ですから、事業と研究開発と知財が三位一体となって動いたということなのです。これを実行したのが電子写真のプロジェクトだったのです。で すから、知財マインド、知財センスが身についたということです。
その後、研究開発体制も、このプロジェクトから育った人達が、いろい ろな研究開発部門に入り、会社全体をそのような方向に動かせた。もっと言え ば、その当時関わった人達が、だんだん偉くなって、研究の責任者になったり、あるいは事業の責任者になったり、最後は経営者になった。私も同じ時代で、ど んどん一緒に歩いて行けたので、 最後は、知財経営という立場になりました。いわゆる知識ではなく、体で、事業と知財が大事だと身についています。これが ベースとしてあったので、会社全体の知財経営が割と簡単にいけたのです。
知財経営というのは、一言で言えば、経営資産のひとつに、知的 財産を入れるということ。それだけのことなのです。ヒト、モノ、カネを大事にするの は経営者はみんなやるのでしょうけど、知的資産、知的財産を経営資産の重要な要素として、常時考えて事業を行うということが、知財経営です。(キヤノン は)会社全体が、経営者も含めて、体で知的財産経営というのを身につけていたのです。知財立国などと言われてから、初めて経営者が理解しなくてはいけない なんてことは全くなく、ずっとその前から知財経営を実行しておりました。それが、電子写真プロジェクトの成果なのです。
ですから、研究 開発と事業を成功させるための知財戦略を考えたら、事業と研究開発、知財の三位一体の状態の活動が非常に大事なのです。業界によっ て多少違いますが、我々の業界の商品をみると、ひとつの商品の中に知的財産がいっぱい入っています。その中で事業競争力に一番影響のある技術は、自社開発 しているかもしれませんが、それについては第3者にまねされないように、知的財産で参入障壁を徹底的に築かないといけない。これが三位一体の活動で大切で す。そして、実施技術の参入障壁を形成するのです。さらに事業のワンサイクルに渡っての参入障壁も形成するのです。そこまで考えて権利化する発明者は普通 いません。発明の権利化において大事なのは、実施技術の参入障壁を作ることも大切ですが、事業参入障壁を作ることも非常に大事なのです。
先ほどの例によりますと、実施したのは一つのプロセスだったのですが、4通りのプロセスの特許出願をした。これが事業参入障壁です。代替技術で、実施技術じゃないけど代替技術で実施するのを防ぐという意味での参入障壁です。
もうひとつは、昨年あたり最高裁判決が出て話題になったけど、インクジェットプリンタのリユースカートリッジ。これは同業者ではないですね、異業 種からの参入であった。ゼロックスも事業形態はレンタルやリースなのです。売り切りはしておらず、リース・レンタルはサービスがメインの稼ぎどころの一つ です。だが、第三者がサービス業に参入してくる。お客さんにそういう第三者のサービスを受けるなというと独禁法に触れてしまう。ゼロックスも困ってしま い、部品を提供しないというと、それもだめだということになって、結局提供することになった。そういう参入を防ぐのは やっぱり知財しかないのです。どう したら、知財で、そういう参入を防げるか。同業ではないその企業の参入形態をよく研究して、そのビジネスごと直接侵害だといえるような権利を取らないとい けない。これが、参入障壁の権利の形成なのです。これを怠ると事業の優位性など持続しない。よく、知的財産はイノベーションに貢献すると言われるが、イノ ベーションの結果の優位性を持続的にすることが、知的財産の役割だと私は思っています。知財の役割は、一時の優位性だけを作るだけなら要らないのです。一 時の優位性だけですぐ参入を許したら、何のために研究開発に多くの人材を投入し多額の研究開発費を投入したのか、何の意味もなくなってしまう。ですから、 事業の優位性の持続を図ることが知財経営で一番大事なポイントです。
(次号に続く)

丸島 儀一
・所属・役職
キヤノン株式会社顧問、金沢工業大学大学院知的創造システム専攻 教授、
東京理科大学専門職大学院客員教授、早稲田大学ビジネススクール 非常勤講師
・専門分野
弁理士、知的財産戦略
・略歴
早稲田大学卒業後、キヤノンカメラ(現キヤノン)入社、弁理士登録、特許部長、
特許法務本部長、製品法務委員会委員長、役員時代には新規事業推進本部長、
研究開発、国際標準も担当、専務取締役を経て、2000年から同社顧問。
政府の知財改革関連審議会、委員会委員、各種団体の知的財産関連の要職や委員
を歴任している。
・著書・訳書など
『キヤノン特許部隊』丸島儀一著、光文社
『知財、この人にきく (Vol.1)』丸島儀一著、発明協会
『知財立国への道』内閣官房知的財産戦略推進事務局編、共著、ぎょうせい