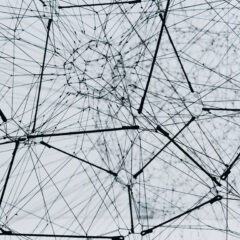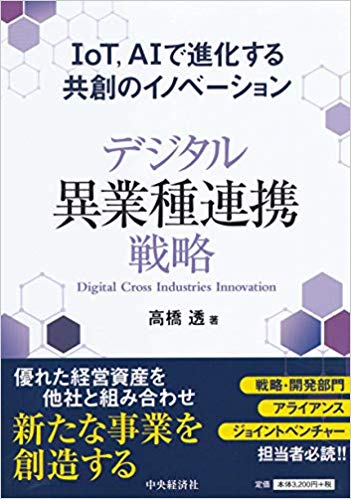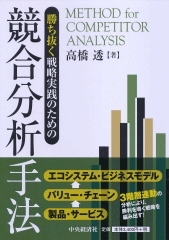ベンチマークでつくりだす競争優位
■オリンピックアスリートたちの戦い
ロンドンオリンピックの開幕まで10日を切り、テレビ各局ではオリンピック関連の番組が多くなってきた。そうした中、NHKでオリンピックに出場する何人かのアスリートを取材した番組を放送していた。強く印象に残った場面がいくつかあった。
その一つは、陸上男子100mの金メダル候補と言われるジャマイカのウサイン・ボルト選手である。肩を大きく上下させる独特のフォームは持病の脊椎側湾症によるもので、このフォームによって曲がった背骨とのバランスを取っているとのことだ。また短距離選手としてはスタートに不利と言われている190cm以上の身長を、自分独自の工夫を考え抜いてむしろ強みにしている。そして病気や弱みを乗り越えて世界記録を更新し優勝するために、過酷なトレーニングでそれを実現させる。番組では、激しいトレーニングから競技場のトラックで嘔吐しているボルト選手の姿もあり、そのシーンは衝撃であった。
もう一つは、2012年1月の 全日本卓球選手権・女子シングルスで初優勝した福原愛選手。現在世界ランキング5位と、ロンドンオリンピックで十分にメダルを狙える位置につけている。中国はじめ競合チームも、福原選手の練習ぶりをビデオで撮影して戦い方を研究していた。福原選手のオリンピックでの勝利への課題は打ち込むボールのスピードを上げること。そのために脚力を向上させることが必要とされ、足の部位ごとの筋トレを毎日相当の時間行っていた。筋トレ、さらに10時間以上の卓球のトレーニングはオリンピック直前まで行われ、本人も「オリンピックまでに右腕がちぎれそう」と、練習直後には倒れ込んで右肩をアイシングしている姿が見られた。5歳の頃からマスコミでよく見てきたあのかわいらしい表情が、今は苦しさで一杯であった。しかしながらインタビューに答える姿からは、厳しい練習を乗り越えて試合で勝つ強い精神力を感じた。オリンピックまでの毎日、毎時間が勝負で、やるべき事をキチンとこなさなければならない、少しも無駄は許されないという強さだった。
同じく卓球代表の19歳、石川佳純選手も、大舞台であるオリンピックのプレッシャーとの精神的な戦いを強いられており、今それを乗り越えようとしている。サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、米国との練習試合での敗退をバネにして、米国をはじめとした競合の研究を行い、再び凌ぐための作戦をたて練習を重ねている。
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。