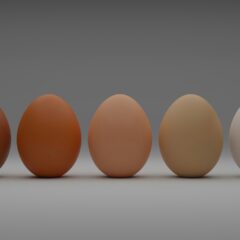ブレークスループロジェクトを組織化するための条件(4)

行動指針を持つ(明確な行動規範)②
■行動することでマインドセット・認識を変える
個人でも組織でも、行き詰まりや停滞を感じるときがあります。それは、周囲の環境の変化に自身のマインドセットあるいは認識が追い付いていないという「ズレ」に起因する場合が多いと思われます。ここでのマインドセット・認識とは、社会や市場をどう捉えるかという思考のパターンであり、パラダイムとも言います。
例えば「日本の地方では過疎化が進み、限界集落が急増する」というのもひとつの認識です。でもそれを、「日本の地方では人口が減少し、自然環境と共生できる時代になる」という認識に変え、それを前提にパーパスを設定したらどうでしょう。課題への取り組みはまったく違ったものになります。
マインドセット・認識は、行動することによってさらに変わります。地方の人口減少の例でいうと、例えば、「青森、秋田、岩手の東北三県を2週間かけて視察し、地域の人と実際に話してみる」といった行動をとることで、マインドセット・認識は大きく変わるはずです。
このように上位概念であるパーパスを意識しつつ、行動を通してそれを実感することで、マインドセット・認識が大きく変化し、これが物事を進展させます。流れで示せば、「パーパスを理解する(思考で理解)→行動指針の一つを実行する→パーパスと成果を実感する→マインドセット・認識が変わる→さらに行動する→さらにパーパスと成果を実感する」といったように、人や組織は加速度的に変化・進化していくのです。繰り返せば、行動指針とは、実際の行動を通じてマインドセット・認識を変化させ、強化するためのものです。
思考だけでなく「行動すること」を通じてマインドセット・認識を変えることの効果はけっして小さくありません。よく「まず行動してみよう」「行動すれば自然と変わっていく」などと言われるのはそういうことです。
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。