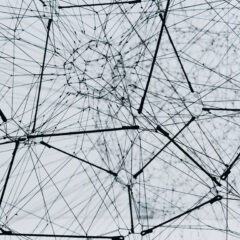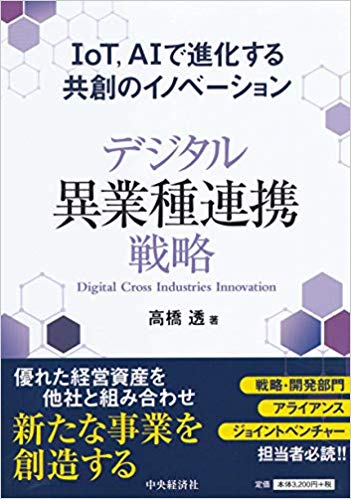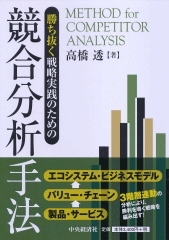東京大学大学院 山本義春教授対談 健康情報学とヘルスケアIoTへの期待
昨今、健康寿命延伸がホットワードになりつつありますが、これからは個人が老年時に「どのようになりたいか」をイメージし、コントロールしていく時代です。私が設立から携わっているヘルスケアIoTコンソーシアムでも、試験環境を構築し、実証実験のフェーズに突入しました。
今回対談させていただいた山本先生は、IoTが出てくる以前から、心と体の状態の測定、分析をする健康情報学をご専門に研究されています。健康情報学の歴史と、これからのヘルスケアIoTへの期待について伺いました。

今回は東京大学大学院山本義春教授(右)との対談です。
高橋:山本先生にはヘルスケアIoTコンソーシアム(通称HIT)会長をお勤めいただいていますが、先生が健康情報学に至るまでのご経歴やどのような研究をされてきたかをお聞かせいただけますか。
山本:大学院時代から、呼吸や循環系の生理学の研究をしていました。呼吸ごとの酸素摂取量や循環の変化について研究をする中で、大規模データ分析の必要性に直面し、そこから実際の複雑な生体から特徴量を抽出するための数理解析のモデルの適用や、独自の解析手法を研究するようになりました。東京大学で博士課程修了後、カナダのウォータールー大学に4年間在籍している間も、応用生理学分野の特徴量抽出の仕事を行い、1990年代には生体情報処理が本業のようになっていました。今でもそうですが。

21世紀に入ってからは人の行動の複雑な変化を分析する必要性に気づき、またその指標となるデータを測定できる機器が出てきたこともあって、人間の行動の変化の研究をするようになりました。米国の慢性疲労症候群の第一人者との共同研究で、患者さんの症状を加速度計も利用したEcological Momentary Assessment(EMA)という手法で測れるように独自開発しました。現在のApple Watchのようなもので、このようなEMAの臨床応用は、当時では先駆けであったと思います。
そのようなアプローチから、慢性疲労症候群では動きの鈍さを表す特徴量抽出を、またうつ病や躁うつ病など精神疾患の患者ではそれぞれ特徴的な行動パターンを、中村亨先生(現・大阪大学基礎工学研究科特任教授)と調べ、症状と関連した特徴を大量のデータから抽出する手法を開発しました。心拍などからも特徴抽出することができるので、最終的にはリアルタイムに症状を把握しその場で介入することを目指しています。2002年から現在まで、メーカーと臨床用のウェアラブルの仕様を検討してきましたが、メーカー側も撤退や死の谷等があり、なかなか進まない面もありました。ウェアラブルが出始めた当時は、センサの通信環境、バッテリー、小型化等の課題がありましたが、ここ数年は技術的にも随分と向上がみられ、日常の中で生体情報をリアルタイムで測定し、通信、介入することができるようになってきましたし、実際にそういった研究開発も行っています。
EMAは日常生活下の人の生理、環境、行動や心理状態を評価することをコンセプトとしていますが、ほんの少し前までは技術的に困難な面もあり、実際には心理評価のみにとどまっていました。IoTが普及した今、本来の意味でEMAが機能を発揮できるようになったと思っています。今後は、大量にとれるデータをどのように分析するかが鍵になりますが、私どもの場合はその分析を先がけて研究していたので、データさえ得られればアドバンテージ(答え)を持っている状況です。

記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。