大阪大学大学院 中村亨特任教授対談
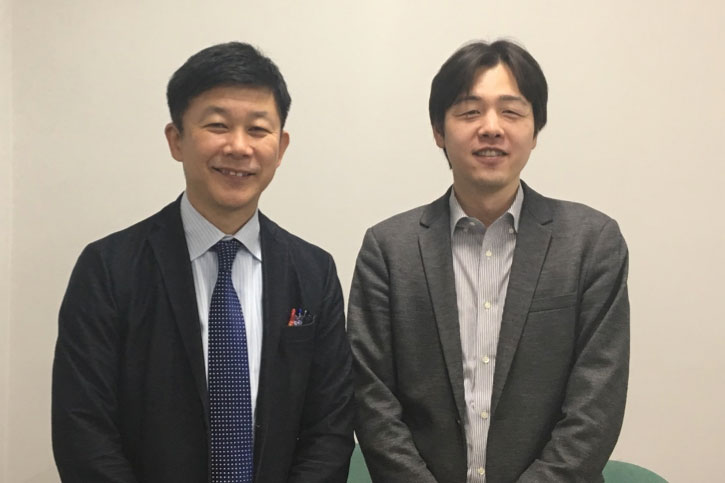
生体信号・へルスケアデータ利活用の課題と展望②
前回に引き続き、私ニューチャーネットワークス・高橋透による、大阪大学大学院基礎工学研究科附属産学連携センター・特任教授 中村亨先生へのインタビューのまとめです。インタビューの中で印象的だったのは「生体は分からないことだらけです。機械とはシステムや制御方式が全く異なるので、常識が適用できず、哲学的になる面もあります。」という言葉です。その分からないことだらけの生体に、ヘルスケアIoTコンソーシアムという産学連携の組織を通じ、協業しながら多面的にアプローチしていく中村先生の活動をご紹介いたします。
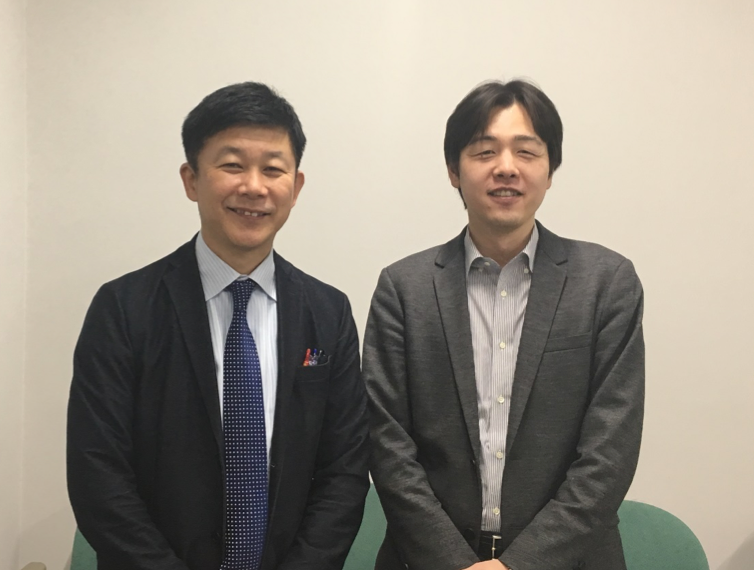 大阪大学の中村亨特任教授(右)との対談です。
大阪大学の中村亨特任教授(右)との対談です。
高橋:昨今のトレンドとして、モノづくり側(メーカー)が様々な製品にセンサを組み込んでいます。実際に製品を使う消費者にどうなってほしいかがイメージされて作られていれば良いですが、単純に短期的な利便性や流行、また過去に検討されたファンクションに則って開発されたものでは、消費者は感動しません。センサの組み込まれた製品を使うことによって行動にどのような影響や変化がもたらされ、こうした方がよいという未来予測まで与えられれば、消費者も感動し、対価を支払います。
中村:それが理想ですが、現状はガラパゴスな面があります。メーカーは「他社に比べて精度良いデータが取れた」、「計測期間が伸びた」といったことを競っている状態で、それも大切なことではありますが、そればかりに集中していては新しい機器は普及せず、市場も成長しません。
高橋:状況が変化する中で様々なニーズに対応しようと新しい機器が出てきている一方で、昔からある占いはあり続けています。今でも毎年初詣に行くと多くの人が引くように、お寺や神社のおみくじは大きな収入源になっています。占いやおみくじのように「こうした方が良い」と示す内容には、皆非常に関心を持っているのです。「こうしてはいけない」「こうしたらもっとよくなる」というアプローチには人間は心を開いているので、機器等の“モノ”もそこに働きかけていかなければなりません。言い換えると、モノもそのように作られていれば、とても楽しいものになります。
中村:個人に適合し、その人を良く知り、誰よりも分かってくれるデバイスやシステム、アプリケーションであればとても面白いですね。エビデンスを出して信頼を得ていくことも重要ですが、個人に適合していくことで信頼を獲得していくことは、「他のモノではダメだ」というように、個人に価値を認められるという面が素晴らしいですね。
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。











