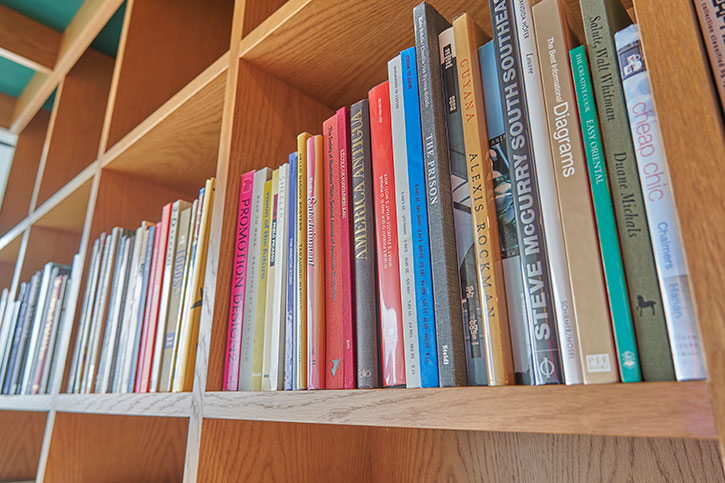
「異業種連携による新規事業開発」アイデア出しまでは進めても事業化は簡単ではない
■なぜいま異業種連携が盛んなのか
IoT(Internet of Things)が本格的に進むと、これまでの「業界」という枠組みはますます希薄となります。しかし多くの企業は、旧来の「業界」という枠の中で、市場シェア競争を行い、そこで勝つための事業戦略を構想し、実行します。しかし全く異なる業界もしくはビジネスモデルで、その「業界」自体が侵食されます。それさえ気づかず既存の戦略や施策を強化しようとしています。
自動車業界に対するUberなどのシェアリングサービス、小売業界に対するAmazonなどのECビジネス、食品業界に対するダイエット関連ビジネス、医療業界に対するヘルスケアサービスなど既存の業界に対して破壊的に新規参入する例はますます増加しています。
新規参入のうちの多くが、異業種が連携したエコシステムやビジネスモデルによるものです。競合が一つの製品やサービス、企業ではなく、異業種で構成された仕組み、システムなのです。したがって従来の経営学の競合分析の概念も当てはまらず、極めて認識し難いのです。人によりますが、特に高齢の経営者の感覚、感性では把握できないと思います。過去の成功体験があればなおさらです。
そこで最近注目されてきたのが、異業種連携による新規事業開発です。エコシステムやビジネスモデルは一社では構築できません。また既存の業界の枠組みでの発想を変え、新たな発想をするには自社とは異なる業種の人とのディスカッションが欠かせません。多様な考え、思考が創発的に結びつき、そこから新たな発想が生まれ、新規事業開発の可能性が見えてくる。そんな期待からセミナー会社、マネジメント団体、コンサルティング会社、大学、自治体などの多くの組織が異業種連携セミナーを開催しています。
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。











