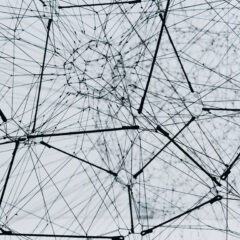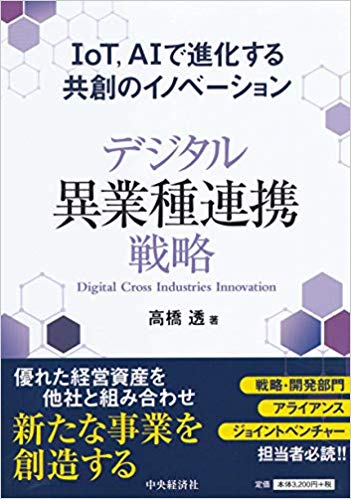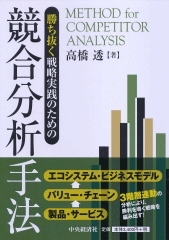高利益を達成するための生産財マーケティングとは(4)
ニューチャーネットワークス 代表取締役
高橋 透
先月の日経ビジネスの特集「大手は子に従え」(2015年4月13日号)は日本の産業構造の大きな変化を感じさせる内容でありました。日本の大手企業からなかなか画期的な製品が生まれてこない。自前主義の旧来の枠組みから脱しきれず、イノベーションの壁にぶち当たっている。総合電機メーカーなどをみると、なかなか結果のでないB2Cから安定収益の見込めるB2Bにすっかり舵をきっている。その一方、エンドユーザーニーズを素早くくみ取り、画期的な製品を繰り出すモノ作りベンチャーが続々登場。かつての大手が開発を牽引する「主」の立場から、ベンチャーに言われたとおりに技術や部品を差し出す「従」へ。この主役交代の歯車は既に回転を始めたとのことです。
メルマガ会員登録
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。