技術主導のモノづくり企業の7つの落とし穴
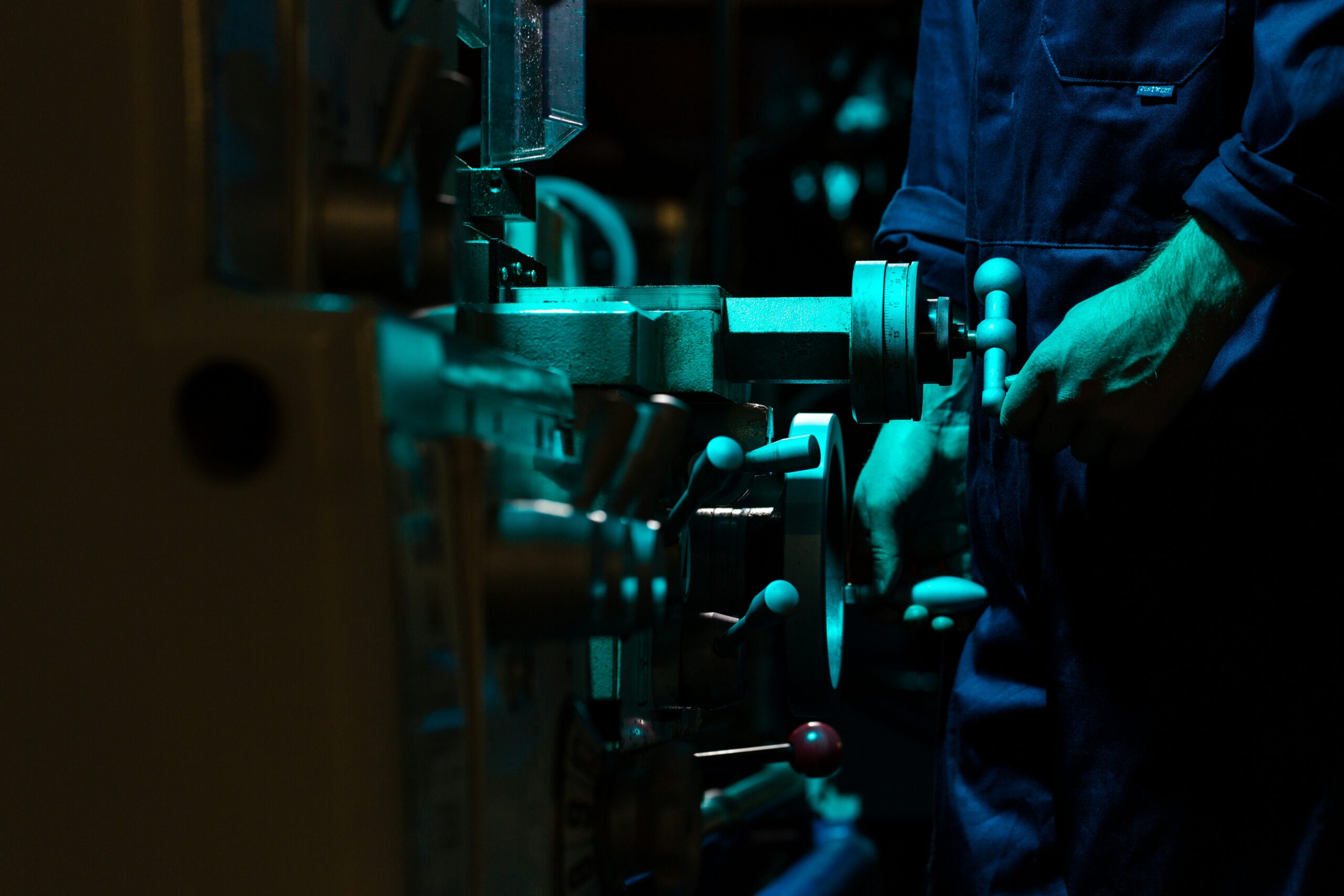
価値創造に挑戦する人材・ノウハウが少なくなっていないか?
■価値創造に挑戦する人材・ノウハウが少なくなっていないか?
既存事業が成熟し低迷に悩む企業の多くは、新製品・新事業開発の必要性を訴え、開発プロジェクトを立ち上げるのはもちろん、イントレプレナーといった社内起業制度を導入するなど様々な取り組みを行なっています。しかしながら、結果が出ないという理由でわずか2~3年で終了したり、終了しないまでも予算や時間などの投入資源を大幅に削減したりするケースが少なくありません。これでは、開発過程でせっかく獲得した経験やノウハウが蓄積も伝承もされず、人材育成につながりません。
しかし、成功するのは1000に3つと言われる新製品・新事業開発の難しさを考えたとき、人材が育成できていない中で、どうやってこれを成功させるというのでしょうか。
既存事業の収益が低迷しているのですから、結果を急ぐ気持ちはわかります。しかし、新製品・新事業開発を行うのは「人」です。その育成には一定の時間がかかることを理解しなければなりません。
このような残念な現象が起こる背景には、日本企業の多くがバブル経済崩壊後、腰を据えて新製品・新事業開発に取り組んでこなかった、という現実がありそうです。円高、リーマンショック、東日本大震災と厳しい環境が続く中で、多くの企業は事業の選択と集中を行ない、製造工場の海外移転、事業の売却、組織リストラなどを断行してきました。ただ困難を乗り越えるのに精いっぱいで、その間、新製品・新事業開発に投資する余裕がなかったという面もあるでしょう。実際、役員全員に新製品・新事業開発の経験がないという企業も少なくありません。
そういう企業・組織においては、「新しい価値」とはどうしたら創造できるのか、経営トップはじめ誰一人わかっていない、というのが現実だと思います。気づけば開発担当の部署もない、新しいことに挑戦する風土もない、指示待ちで受け身の人ばかり、とういう状況ではないでしょうか。
昨今、新卒の就職は少子化の影響で売り手市場ですから、新しい風を入れてくれる若い人材はなかなか集まりません。モチベーションが高い学生は大手企業を避け、スタートアップ企業やコンサルティング会社を選択する傾向が高まっています。さらには、学生のうちに起業する人も多くなってきました。
記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。
是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。
メルマガ会員登録はこちらです。
会員の方は以下よりログインください。











